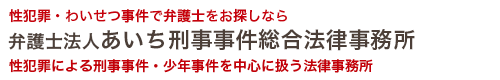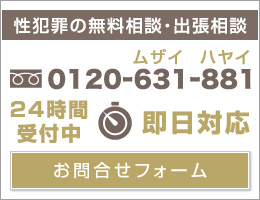【事例解説】自身の養子と性交し、監護者性交等罪で逮捕(後編)
自身の養子と性交し、監護者性交等罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
この後編では、被害者の供述等の証拠について争われた例を解説します。

事例
Aは、自身と同居している養女のV(16歳)と、今年の4月~5月ごろにかけて複数回性交をしました。
Vが母親に被害を告白したことをきっかけに、Vは児童相談所に保護され、Aは逮捕されました。
(フィクションです)
自身の養子と性交し、監護者性交等罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
この後編では、被害者の供述等の証拠について争われた例を解説します。
実行行為の存否について
今回の事例では、第三者による犯行の目撃等がなく、さらにAが性交の事実を否定しているとします。そのような場合は、被害者の供述や、客観証拠などによって犯罪の実行行為があったことを認定することになります。
ここで、被害者の供述の信用性などが争われた判例(福岡高判令和3・10・29)を紹介しながら、被害者の供述の信用性の判断のポイントを解説します。
なお、この判例の事案は、今回の事例に近いものですが、被害者(以下Vとする)が14歳であったことと、被害者が軽度知的障害段階(IQ77,精神年齢11歳4か月)であったことが今回の事例とは異なっています。
この判例では、被害者の供述の信用性を判断するうえで、
①被害者の供述は客観的証拠によって裏付けられているか否か
②被害者の供述に具体性・迫真性があるか否か
③被害者の供述に不自然・不合理な点があるか否か
④被害者に虚偽供述の動機があるか否か
が審理されました。
①まずVの供述を被害者の外陰部の損傷という客観的証拠によって裏付けることができるかどうかが争われました。
1審では、損傷は性交によらなくても起こり得ること、損傷の状態から挿入された物を同定することはむずかしいこと、もとより、Vの身体の損傷からそれを生じさせた者を推認することはできない、などの理由でVの供述が客観的証拠によって裏付けられているとは言えず、信用性を備えていないと結論付けました。
これに対し、控訴審では、性暴力や虐待事案に関する生体鑑定の法医学の専門的知見をもつ医師の供述から、むしろ損傷はVの供述を裏付ける客観証拠と認められる可能性が高いとしました。
②次に、Vの供述が実際に体験しなければ供述できないほどの具体性・迫真性があるかどうかについては、未成年であることや軽度知的障害であることを考慮すると、具体性・迫真性に欠けるからといって直ちに架空の被害を創作した合理的疑いが生じると推認するのは適当ではない、としたうえで、Vの供述のほぼすべてが検察官の誘導尋問によって引き出されたものであるともいえない、としました。
③さらに、1審では、AやVと同居している他の家族が、犯行に一切気付かなかったというのは不自然・不合理である、としましたが、控訴審では、VはAを恐れて抵抗せず、起きていることがAにばれないようにしていたと供述していることや、Aにおいても発覚を防ぐため細心の注意を払っていたとみるのが自然であり、他の家族が気付かなかったとしても不自然・不合理であるとはいえないとしました。
④最後に、虚偽供述の動機があるか、については、VがAに悪感情を抱いていたことから、ストレス源であるAを悪者にしようと考え虚偽の供述をしたという可能性について、それなりに合理性があるというのが1審の判断でした。
しかし、控訴審ではVの被害申告の経緯には特に作為的なものがうかがわれず、むしろ慎重で真摯なものであったとみる余地が十分にあるとして、さらに審理を尽くすべきとしました。
この事案では、最終的にVの供述の信用性が認められ、Aは懲役7年の実刑となりました。
(参考図書:『裁判例に学ぶ刑法各論Ⅰ 個人的法益編』)